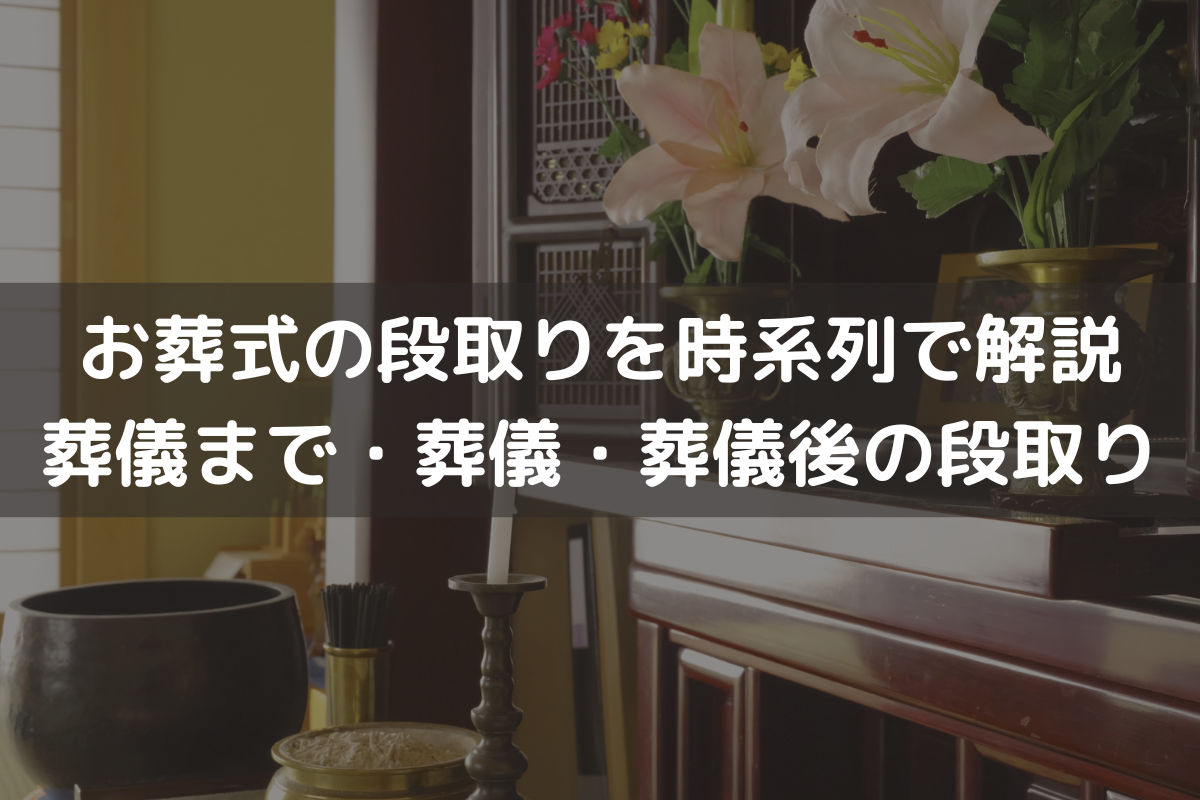ご家族が亡くなると、ご逝去直後からお葬式へ向けてさまざまな準備や対応が必要となります。
では、ご逝去からお葬式までは、どのような段取りとなるのでしょうか?また、お通夜やお葬式の当日は、どのような段取りで進行するのでしょうか?
今回は、ご逝去からお葬式までの段取りと、お通夜・お葬式当日の段取りについてくわしく解説します。あらかじめお葬式全体の段取りを掴んでおくことで、落ち着いて準備や当日に臨みやすくなるでしょう。
なお、当サイト「家族葬のアイリス」は全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご家族のご逝去後にご連絡をいただいたら、すぐに担当者がかけつけてサポートを開始します。お電話は、24時間365日受け付けているため、お葬式の段取りでお困りの際は家族葬のアイリスまでお気軽にご連絡ください。
【概要】ご逝去からお葬式までの基本の段取り・日程
はじめに、ご逝去からお葬式までの全体の流れについて、概要を解説します。
- ご逝去当日:搬送や安置、打ち合わせ
- ご逝去翌日:お通夜の準備と、お通夜
- ご逝去翌々日:葬儀・告別式と火葬
ご逝去当日:搬送や安置、打ち合わせ
ご逝去当日は、ご逝去場所から安置場所にご遺体の搬送をするとともに、葬儀社の選定や喪主の決定、葬儀社との打ち合わせなどを行います。併せて、近親者や勤務先などに、ご逝去の連絡をします。
ご逝去翌日:お通夜の準備と、お通夜
ご逝去の翌日には、お通夜の準備とお通夜を行います。お通夜は、夕刻の18時や19時頃からの開始とすることが一般的です。
なお、お通夜は原則として、火葬の前日に行うものです。そのため、日程を決める際はお通夜から決めるのではなく、まずは火葬をする日を決め、その前日の夕刻をお通夜とすることが多いでしょう。
ご逝去翌々日:葬儀・告別式と火葬
ご逝去の翌々日に、葬儀・告別式と火葬を行います。
厳密には、葬儀は宗教儀式であり告別式は別れを惜しむ儀式であるという点で区別されますが、実際には「ここまでが葬儀、ここからが告別式」と区別されず一連の儀式として行われることが一般的です。葬儀・告別式の後は火葬場へ向けての出棺となり、火葬場へ付いたらご遺体を荼毘(だび)に付します。
前提として、葬儀・告別式と火葬は同日に行うのが基本です。また、葬儀・告別式の開始時刻は火葬場の予約時刻から「逆算」して決めるのが一般的であり、午前中からの開始となることが多いでしょう。
なお、葬儀・告別式と火葬は必ずしもご逝去の翌々日となるわけではなく、さまざまな要素によって日程が左右されます。お葬式や火葬の日を左右する主な要素は、次でくわしく解説します。
お葬式の日程を左右する主な要素
お葬式の段取りを決めるにあたって、はじめにお葬式の日程を決めなければなりません。ここでは、お葬式の日程を左右する主な要素について解説します。
- 法律
- ご逝去場所
- 火葬場の空き状況
- 近親者の都合
- 僧侶の予定
- 友引の日程
- 参列のしやすさ
- 斎場の空き状況
- 地域や宗派の慣習
法律
1つ目は、法律です。
日本では法律(墓地埋葬法)の決まりにより、原則としてご逝去から24時間は火葬ができないこととされています。また、火葬場は原則として午後5時には閉まります。
そのため、仮に6月1日の17時頃に亡くなった場合には6月1日の火葬はできないのみならず、6月2日の火葬も困難でしょう。この場合において最短で火葬ができるのは、6月3日となります。
ご逝去場所
2つ目は、ご逝去場所です。
故人が遠方で亡くなった場合には、お葬式をする場所までご遺体を搬送するために日数を要する可能性があります。特に、海外などで亡くなった場合にはご遺体を航空機に乗せる必要があり、航空機ではドライアイスが使えない関係上、エンバーミングも施さなければなりません。
エンバーミングとはご遺体の防腐を避けるために血液と防腐剤を入れ替える処置であり、これにも日数を要します。そのため、遠方で亡くなった場合には搬送に要する日数も加味してお葬式の段取りをすることとなります。
火葬場の空き状況
3つ目は、火葬場の空き状況です。
火葬場が開いて(空いて)いなければ、その日には火葬のしようがありません。火葬場の休日は地域によって異なるものの、「土日休み」ではなく、一般的にお葬式の施行が避けられる友引を休みとしていることが多いでしょう。
また、火葬場の休日の翌日は混み合いやすく、予約が取れない可能性もあります。特に、年末年始は火葬場が長期休みとなるため、これも加味してお葬式の段取りをしなければなりません。
近親者の都合
4つ目は、近親者の都合です。
故人の配偶者など非常に近しい関係にある人の都合がどうしてもつかない場合には、近親者の都合に合わせてお葬式の日程を決めることがあります。たとえば、近親者が海外におり帰国までに日数を要する場合や、受験日など非常に重要で日程を変更できない用事がある場合などがこれに該当します。
僧侶の予定
5つ目は、僧侶の予定です。
菩提寺がある場合、菩提寺の僧侶に読経をお願いすることとなります。仮に僧侶の都合が付かなくても、他の僧侶を紹介してもらえる場合が多いでしょう。
しかし、お盆やお彼岸、年末年始は僧侶の予定が埋まりやすく、代わりの僧侶も見つからない可能性が高くなります。このような場合には、僧侶の都合に合わせて葬儀の日程を調整します。
友引の日程
6つ目は、友引の日程です。
友引は六曜の一つであり、本来は仏教や神道などの宗教とは何の関係もありません。また、友引は「共に引く(つまり、勝負がつかない)」という意味であり、「友を引く」という意味でもありません。
しかし、日本ではその字面が縁起が悪いと考えられ、友引のお葬式(火葬)は避けられる傾向にあります。そのため、ご逝去の翌々日が友引にあたる場合には、友引の葬儀を避けるため、日程を調整することが多いといえます。
参列のしやすさ
7つ目は、参列のしやすさです。
葬儀の参列者が多いと予想される場合において、参列者の多くが平日の参列が難しい場合には、参列のしやすさを考慮して土日にお葬式をする場合があります。
なお、お葬式は日中に営まれる一方でお通夜は夕刻であることから、お通夜を中心に参列されるケースも少なくありません。そのため、お通夜に多くの参列者が訪れることを見込み、土日にお葬式をずらすことまではしない場合もあります。
斎場の空き状況
8つ目は、斎場の空き状況です。
希望する斎場に空きがない場合には、斎場の空きに合わせてお葬式の日程を調整することとなります。
なお、家族葬のアイリスは全国の多くの斎場と提携関係を結んでいるため、混み合いやすい時期であっても空きのある斎場を見つけやすいといえます。ご家族が亡くなりお葬式の段取りでお困りの際は、家族葬のアイリスまでご相談ください。
地域や宗派の慣習
9つ目は、地域の慣習や宗派の考え方です。
地域や宗派によっては、そもそも「ご逝去の翌々日が火葬」という考えがスタンダード出ない場合もあります。その場合は、地域や宗派の考えに沿ってお葬式の日程を検討するとよいでしょう。
ご逝去からお葬式までの段取り:ご逝去当日
ここからは、ご逝去からお葬式までの段取りについて、くわしく解説します。
まずは、ご逝去当日の段取りです。ここでは、入院中に亡くなった場合を前提に、解説を進めます。
- 臨終
- 末期の水
- 近親者への連絡
- 葬儀社への連絡
- 菩提寺への連絡
- 死亡診断書の受け取り
- 安置場所への搬送
- 安置
- 喪主の決定
- 葬儀の打ち合わせ・葬儀プランの検討
- 参列予定者などへの連絡
- 死亡届の提出
- 遺影写真などの準備
臨終
ご逝去が確認されると、医師から死亡を確認した日時が告げられます。
末期の水
ご逝去後は、「末期の水」をとります。末期の水とは、ご逝去直後に、臨終に立ち会った近親者が故人の口元を水で湿らせる儀式であり、「死に水をとる」といわれることもあります。これは、医学的な処置ではなく、故人が安らかに旅立てるようにとの願いを込めて行われる宗教儀式です。
末期の水をとるか否かは宗教・宗派によって異なります。仏教や神道では行われることが多いものの、浄土真宗では行われないためあらかじめ確認しておきましょう。
近親者への連絡
ご逝去が確認されたら、臨終に立ち会っていない近親者にご逝去を知らせる連絡をします。
なお、家族葬など参列者を限定したお葬式を予定している場合には、この段階での連絡は参列を希望する相手に留めた方がよいでしょう。また、連絡をした相手にも、「家族葬を予定しているため、一定の相手以外には連絡しないでほしい」旨を伝えることをおすすめします。
ご逝去の連絡を受けた人は葬儀に参列すべきと考えることが通常であり、多くの人に連絡をしてしまえば思いがけず多くの人が参列に訪れ、対応に追われる事態となりかねないためです。
葬儀社への連絡
近親者への連絡と並行して、葬儀社に連絡をします。これほど早いタイミングで葬儀社への連絡が必要となる理由は、ご遺体の搬送を依頼する必要があるためです。
病院で亡くなると、その後は病院内の霊安室にご遺体が安置されます。しかし、霊安室が使用できるのは数時間程度であり、この時間内に他の安置場所までご遺体を移動させなければなりません。
とはいえ、自家用車にご遺体を乗せて搬送することは、現実的ではないでしょう。そこで、ご遺体を搬送できる寝台車を持っている葬儀社に連絡をとり、ご遺体を搬送してもらう必要が生じます。
葬儀社は病院から紹介されることが多いものの、その葬儀社への依頼は義務ではありません。大切なお葬式で後悔しないよう、信頼できると感じた葬儀社を選定して連絡することをおすすめします。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご逝去のご連絡をいただいたら、すぐに担当者が駆け付けてサポートします。信頼できる葬儀社をお探しの際は、家族葬のアイリスまでご連絡ください。深夜や早朝であっても、ご遠慮いただく必要はありません。
菩提寺への連絡
葬儀社への連絡と並行して、菩提寺に連絡をします。菩提寺に連絡して、僧侶の予定を確保する必要があるためです。
死亡診断書の受け取り
病院を出る前に、医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書はA3の用紙の右半分に記載されており、同じ用紙の左半分は死亡届の様式です。この用紙は死亡届として市区町村役場に提出することになるため、紛失しないようご注意ください。
安置場所への搬送
葬儀社の担当者が到着したら、ご遺体を安置場所まで搬送します。安置場所は、ご自宅または葬儀社の安置施設とすることが一般的です。葬儀社の安置施設を利用する場合、安置施設の利用料が別途発生する可能性もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
家族葬のアイリスは、自宅葬プランを除き、最大3日分の安置施設利用料をはじめから葬儀プランの料金に含んでいます。
安置
安置場所に到着したら、ご遺体を安置します。ご遺体の枕元には、「仮祭壇」とも呼ばれる枕飾りを設置します。
家族葬のアイリスでは枕飾り一式の費用をはじめから各プランの料金に含んでいるため、安心してご利用いただけます。
喪主の決定
ご遺体の安置と並行して、喪主を決めます。喪主を誰とするかは、法律などで決まっているわけではありません。一般的には、故人にもっとも近しい人を喪主とすることが多いでしょう。
原則として、配偶者がいる場合は、原則として配偶者が喪主を務めます。配偶者がいない場合や、配偶者はいるものの高齢などの事情により喪主を務めることが難しい場合には、故人の子が喪主となります。
葬儀の打ち合わせ・葬儀プランの検討
喪主が決まったら、喪主が中心となり葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀プランを検討します。打ち合わせの際はお葬式全体の段取りを確認するとともに、追加料金発生の有無や、追加料金が発生するケースなどについても確認しておきましょう。
当初提示された葬儀費用が安価である一方で、途中でさまざまな費用が追加された結果最終的な請求額が高額となるなどの葬儀トラブルは少なくないためです。
家族葬のアイリスは各葬儀プランにその葬儀の施行に最低限必要となる物品やサービスをすべて含んでおり、不明瞭な追加料金を請求することはありません。そのため、大切なお葬式を安心してお任せいただけます。
参列予定者などへの連絡
葬儀の日程が決まったら、参列予定者へ葬儀の日時や場所、宗派などを連絡します。すべての関係者に喪主が直接連絡する必要はなく、他の親族などと手分けをして連絡するとよいでしょう。
家族葬など参列者を限定した葬儀である場合には、参列が予定される相手にだけ連絡をします。思いがけず多くの参列者が訪れる事態を避けるため、その他の関係者には、葬儀を終えてから連絡をすることが一般的です。
死亡届の提出
葬儀プランの打ち合わせなどと並行して、市区町村役場に死亡届を提出します。葬儀社のスタッフが提出を代行することも多いため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
家族葬のアイリスでは、死亡届の提出代行費用がはじめから各プランの料金に含まれているため、死亡届の提出代行にあたって追加料金はかかりません。
遺影写真などの準備
通夜当日までに、必要な物品などを用意します。主に用意すべきなのは、次のものなどです。
- 遺影写真
- 棺に入れる副葬品
- 喪服
- 僧侶に支払う現金
- 移動に自家用車を使用する場合、車両の清掃と給油
これらは一例であり、具体的に用意すべきものは、状況や葬儀プランなどに応じて葬儀社から案内されることが一般的です。
ご逝去からお葬式までの段取り:通夜当日
続いて、通夜当日の一般的な段取りを解説します。
- 湯灌の儀
- 納棺
- 斎場の準備
- 親族集合
- 受付
- 通夜
- 通夜振る舞い
湯灌の儀
お通夜の開始時間に先立って、ご遺体の準備を整えます。まずは、必要に応じて「湯灌の儀」を行います。湯灌の儀とは、ご遺体の身体をお湯で拭いて清める儀式です。
衛生上観点から行うものではなく、故人が生まれ変わる準備として行うものであり、宗教的な意味合いが強いといえます。そのため、湯灌の儀は必ず行うものではなく、行わないケースも少なくありません。
納棺
続けて、ご遺体を棺に納める「納棺」を行います。納棺に際しては、ご遺体のお化粧とお着替えを行います。ご遺体の服装は「死装束」とすることが一般的であるものの、生前によく着ていたお気に入りの服などとする場合もあります。
ただし、死後硬直が始まっていると希望する服が着せられない可能性もあるため、着せたい服がある場合にはあらかじめ葬儀社の担当者に確認しておきましょう。
斎場の準備
ご遺体の準備が整ったら、斎場の準備を行います。斎場の準備は葬儀社のスタッフが行うものの、供花の配置の検討や読み上げる弔電の選定、順序の決定などにはご遺族の協力が必要です。併せて、会葬礼状や返礼品なども確認しておきましょう。
親族集合
通夜開始の1時間ほど前に、親族が集合します。集合したら、座席の配置など会場の確認を行います。
受付
通夜開始の30分ほど前から、受付を開始します。ただし、家族葬など参列者が限られている場合には顔を見れば誰であるか分かるため、受付を省略することもあります。
通夜
定刻になったら、通夜を開始します。通夜の一般的な段取りは次のとおりです。
開式
はじめに、開式の挨拶がなされます。この挨拶は、葬儀社のスタッフが行うことが一般的です。
僧侶による読経・お焼香
開式したら、僧侶による読経とお焼香がなされます。
参列者による焼香
続けて、参列者が焼香をします。焼香は喪主から始め、遺族・親族・弔問客の順に行います。
喪主挨拶
通夜の最後に、喪主が参列者に向けて挨拶をします。この挨拶では、参列者によるお礼などを伝えます。
閉式
喪主挨拶が終わると、通夜は閉式となります。通夜の開始から閉式までは、30分から40分程度であることが一般的です。
通夜振る舞い
通夜の後に、参列者に軽食を振る舞う「通夜振る舞い」をすることがあります。通夜振る舞いは、参列者にお礼を伝える意味合いのほか、故人との最期の食事との意味合いもあります。通夜振る舞いは、1時間から長くても2時間程度で散会とすることが一般的です。
ご逝去からお葬式までの段取り:お葬式当日
続いて、お葬式当日の一般的な段取りを解説します。
- 親族集合
- 受付
- 葬儀・告別式
- 火葬
- 骨上げ
- (繰り上げ初七日)
- 精進落とし
ただし、宗派や宗旨によっては流れなどが異なる場合があるため、葬儀社の担当者にあらかじめ段取りを確認しておくことをおすすめします。
親族集合
お葬式開始の1時間ほど前に、親族が集合します。親族が集合したら、会場の最終確認や段取りの確認などを行います。
受付
お葬式開始の30分ほど前になったら、受付を開始します。通夜と同じく、参列者が限られている場合には受付を省略することもあります。
葬儀・告別式
定刻となったら、葬儀・告別式を開始します。葬儀・告別式の一般的な段取りは、次のとおりです。
開式
はじめに、開式の挨拶がなされます。この挨拶は、葬儀社のスタッフが行うことが一般的です。
僧侶による読経・お焼香
通夜と同じく、僧侶による読経とお焼香がなされます。葬儀と告別式を分ける場合、ここまでが葬儀と考えられます。
参列者による焼香
続けて、参列者が焼香をします。喪主から始め、遺族・親族・弔問客の順で焼香をします。
花入れの儀
棺の蓋を閉める前に、棺の中に花を手向ける「花入れの儀」を行います。これが、故人のお顔が見られる最後の機会となります。
釘打ちの儀
棺の蓋を閉め、蓋の四隅を固定する「釘打ちの儀」を行います。元々は「野辺送り」の途中で棺の蓋が開いてしまわないように行われていたものの、近年では棺の性能が向上しており、途中で蓋が開くようなことはほとんどありません。そのため、実用的な意味ではなく、儀式として行われています。
喪主挨拶
棺の蓋を閉めたら、出棺前に喪主から参列者へ向けて挨拶をします。この挨拶では参列者にお礼を伝えるとともに、故人の享年や生前の様子、これまでのお礼、今後の変わらぬ付き合いのお願いなどを伝えることが一般的です。
出棺
喪主挨拶を終えたら、火葬場へ向けて出棺します。火葬場へ同行するのは一部の近親者のみであり、その他の参列者はここで散会となります。
火葬
火葬場に到着したら、ご遺体を荼毘に付します。火葬場についてからはゆっくりお別れをする時間が取れない可能性が高いため、火葬場につく前に心づもりをしておきましょう。火葬には1時間から2時間程度を要するため、その間は火葬場の待合室で待機します。
骨上げ
火葬を終えたら、お骨を拾い上げて骨壺に納める「骨上げ」を行います。骨上げでは遺族が2人1組になって、足元のお骨から順に頭のお骨を拾い上げます。この際、喉仏だけは残し、喉仏は最後に骨壺に納めます。
(繰り上げ初七日)
初七日法要は原則として、ご逝去の7日後に行います。しかし、初七日法要をすべき日とお葬式の日が近いことから、親族の負担を軽減するため、お葬式の当日に初七日法要をすることが少なくありません。この場合には、火葬の後にいったん斎場に戻り、初七日法要を行います。なお、火葬の前に、お葬式の中に初七日法要を組み込むこともあります。
精進落とし
火葬の後には、近親者と僧侶による食事会である「精進落とし(お斎)」を行う場合があります。精進落としでは、1人1膳のお弁当や懐石料理などを用意することが多いでしょう。
お葬式からおおむね1週間以内に行うべき事項・段取り
お葬式の後にも、行うべきことが少なくありません。最後に、お葬式後おおむね1週間以内に行うべき事項について解説します。
- お葬式費用の支払い
- お葬式でお世話になった相手へのお礼まわり
- 電気・ガス・水道料金などの引き落とし先の変更
お葬式費用の支払い
1つ目は、お葬式費用の支払いです。
お葬式費用の支払い期限は葬儀社によって異なるものの、葬儀日から1週間から10日後あたりが支払い期限とされることが多いでしょう。
お葬式でお世話になった相手へのお礼まわり
2つ目は、お葬式でお世話になった相手へのあいさつ回りです。
受付をしてくれた人や弔辞をお願いした人などに、お礼の挨拶を行いましょう。なお、香典返しは原則として四十九日の忌明け以降に行うため、このタイミングでは行いません。
電気・ガス・水道料金などの引き落とし先の変更
3つ目は、電気やガス、水道料金などの引き落とし先の変更です。
金融機関が故人のご逝去をすると、その時点で口座が凍結されます。故人の口座から引き落とされていた公共料金がある場合には、早い段階で引き落とし先を変更しておきましょう。
まとめ
ご逝去からお葬式までの一般的な段取りについて解説しました。
喪主となるのが初めてである場合、お葬式までの段取りが分からず不安に感じることも多いでしょう。全体の段取りを理解しておくことで落ち着いて臨みやすくなり、後悔のないお葬式を実現しやすくなります。
家族葬のアイリスは全国対応で葬儀のトータルサポートを行っており、ご逝去のご連絡をいただいたら、すぐに担当者が駆け付けてサポートを開始します。ご家族が亡くなりお葬式の段取りでお困りの際は、家族葬のアイリスまでご相談ください。
お電話は24時間365日お受けしており、早朝や深夜であってもご遠慮いただく必要はありません。